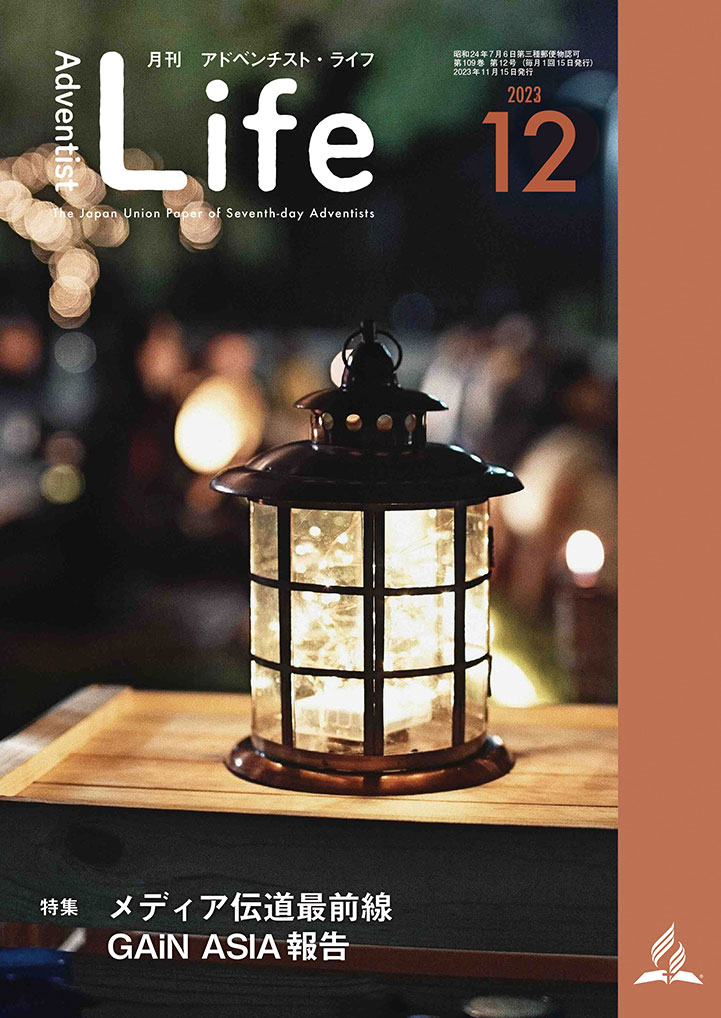「自分の弱さや限界と向き合うことは、人間らしくある術を教えてくれる」1
肉となられて
「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた。わたしたちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていた」(ヨハネによる福音書1章14節)。
同書の冒頭には次のようにあります。「初めに言があった。言は神と共にあった。言は神であった」(1節)。ここに詩的に、されど単刀直入に、言が神であったことが明かされています。言が肉となったとは、すなわち神が肉となられたということでした。
肉であること
神が「肉」となられたことを考えるうえで、クリスマスも間近ですし、神が赤子としてお生まれになったことに思いを巡らせてみましょう。神は、肉は肉でも健康体の30代男性ではなく、無力な赤ん坊となられました。子育てをしたことのある皆さんなら、赤子がどれほどか弱いかをご存じでしょう。保護者なくして、赤ちゃんは生きることすらできません。
赤ちゃんにとっての救いは、自らの無力への無知(あるいは後で忘れること)にあるでしょう。自分が無力であることを知る力も、また実際に力を発揮した経験もないからです。これが、自分で色々としてきたうえでできなくなるとしたら、どれほど辛いでしょうか。
以前、年配の方が「年を取ることは子どもになること」と仰っていました。それを聞いて、年を重ねることの不安や苦悩は、段々と弱っていくのを感じることにあるのかなと思いました。徐々に自立の範囲が狭まり、誰かに頼らざるを得なくなっていくのだとしたら、それは何とも言い難い経験かもしれません。
それを思うと、神が、全知、全能、その他すべてを放棄し、徹底的に肉となり、マリアとヨセフに自らを委ねられた過程には、想像を絶するものがあります。2
「『肉』という言葉は、単なる人間らしさでなく、人間のもろさや弱さをも示す」と、注解者は記しています。3 神は、人々の間に住まうため、人間のもろさや弱さですらもご自分のものとされました。
これは、私たちが望むところの真逆ではないでしょうか。病に苦しんだり、もしくは「罪のない」生活を送ろうとしたりすると、肉が重荷に思えて仕方がありません。ある人は科学の力で、またある人は神の力で、人間のもろさや弱さたる「肉」を克服しようとします。皆、少しでも肉から脱して「神」のようになりたいのです。ところが、そんな神ご自身は、肉となられたというのです。その脆弱なることの一切を引き受けて(そして肉として死に、肉として復活し、そのまま昇天されたのです)。
肉によって
なぜ神は、肉となられたのでしょうか。
「言は肉となって、わたしたちの間に宿られた」とあります(ヨハネによる福音書1章14節)。人類史を通じて、神はさまざまな方法で人々の間に宿られてきましたが、これは唯一無二の出来事でした。肉なる人類の一員として、人々の間に来られたからです。
そして「わたしたちはその栄光を見た」(14節)とヨハネは証ししました。栄光というと、輝かしい光や、燃え盛る炎を思い浮かべるかもしれません。ところが使徒によれば、彼らは肉に神の栄光を見たというのです。その栄光は「父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちてい」(14節)ました。御子は、御父を唯一見て知っておられるお方として、4 神の栄光、すなわちあふれんばかりの「慈しみとまこと」(出エジプト記34章6節)とをお示しになりました。
驚くべきことに、肉であることは、神の栄光をあらわすうえで何の支障もありませんでした。5 「イエスは人の肉をとることで、人間の弱さや無力さを体験され、無力な罪人への憐れみを呼び起こされた」からです。6 それで「われわれは、神がわれわれの試練をよく知り、われわれの悲しみに同情してくださるということがわか」りました。7
むしろ肉となられたことで「神の愛の光」は燦然と輝いたとすらいえるでしょう。8 私たちと肉をともにされたイエス・キリストにおいてこそ、神の栄光は「あらしめられた」のでした。9
肉として
「受肉を通して(中略)キリストは、私たちにまず人間であるように─それすなわち自らの有限性から逃れぬように─と教えておられる」10
キリストを想うとき、私たちは人間であることを享受できます。もろく、か弱き肉においてこそ、神の栄光がにじみ出るのを見せられたからです。11 そこからあふれ出た憐れみと恵み、慈しみとまこととが、どうか肉なる私たちに触れてくださいますように。そして、私たちの欠けたるところから、その御「光が輝き出」ますように(コリントの信徒への手紙二・4章6節)。
1 Tish Harrison Warren, Prayer in the Night: For Those Who Work or Watch or Weep (Downers Grove, IL: InterVarsity Press, 2021), 95
2 神がマリアとヨセフに自らを委ねられたのは、決して形式的ではありませんでした。例えば、時の王がイエスを抹殺しようとした際に、超自然的な介入はあっても、奇跡的な加護や救出はありませんでした。天使のお告げに応えて、実際に赤子を抱えて逃げないといけなかったのはヨセフとマリアでした(マタイによる福音書2章13~15節)。当然、神は未来をご存じだったでしょうし、歴史を導いておられました。しかし、神がこの二人を、赤子のためなら身を挺する人間として信頼しておられたからこそ、二人に御身が委ねられたのもまた事実なのではないでしょうか。
3 Jey J. Kanagaraj, John, NCCS (Eugene, OR: Cascade Books, 2013), 6
4 ヨハネによる福音書1章18節、マタイによる福音書11章27節参照
5 エレン・ホワイトが「おおわれた」とした栄光は、神の「臨在の光」としての栄光です(エレン・ホワイト『希望への光』675~677ページ参照)。
6 Kanagaraj, John, 6
7 エレン・ホワイト『希望への光』677ページ
8 エレン・ホワイト『希望への光』675ページ
9 Edward W. Klink III, John, ZECNT (Grand Rapids, MI: Zondervan, 2016), 122
10 Emmanuel Falque, The Guide to Gethsemane: Anxiety, Suffering, Death, trans. George Hughes (New York: Fordham University Press, 2019), 13
11 ところで、赤子のイエスにも、神の栄光は見られたのでしょうか。思うに、そこに現れた栄光とは、イエスご自身が発揮されたものではなくて、マリアとヨセフから引き出された(あるいは彼らが御父のそれを反映した)栄光だったのではないでしょうか。赤子として無力であることにより、二人の恵みと真理とが呼び覚まされ、神の栄光が示されたのではないでしょうか。
*聖句は©️日本聖書協会

品末拓真/しなすえたくま
静岡生まれ。広島三育学院高校を卒業し渡米。現在は南カリフォルニア教区の日本人・日系人教会牧師を務める。
アドベンチスト・ライフ2023年12月号