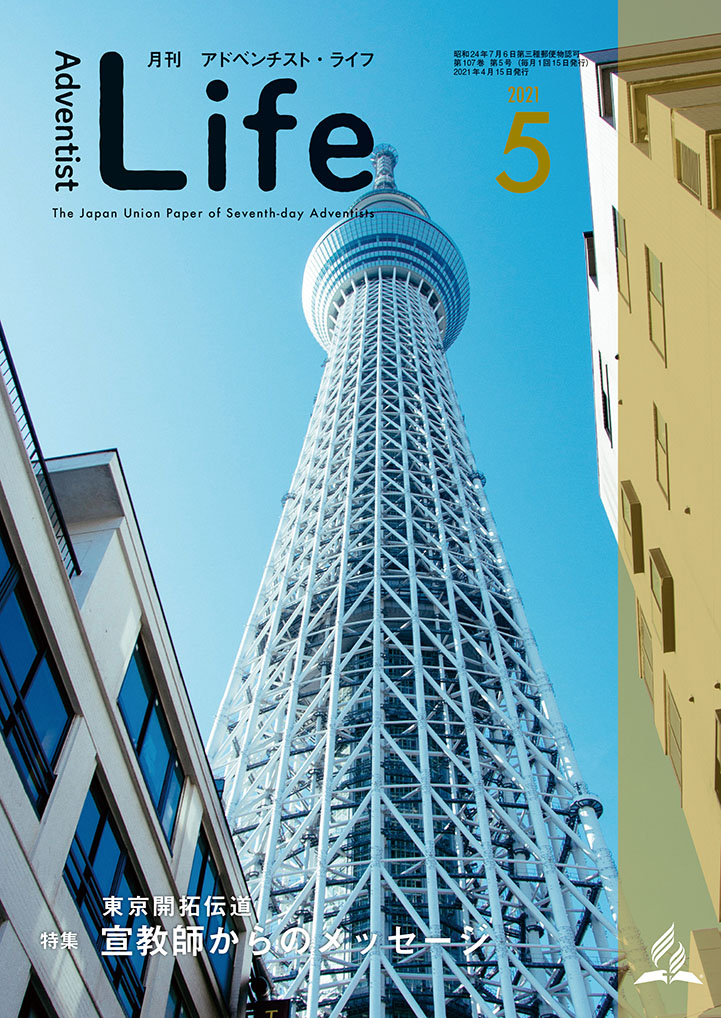「山上の説教」は絵に描いた餅か?
今から二千年も前の世界を、容易には想像できません。生活様式はまるで違うし、なんと言ってもテクノロジーや医療レベルは比較にならないからです。当時は、もしかしたら、今私たちがコロナにおびえているように、風邪程度の病でも“死”を意識したかもしれません。みんな今よりも生きることに必死で、救いや希望を飢え渇くように求めていたのではないでしょうか。
キリストはそのような群衆を憐れまれ、「山上の説教」を語られました。その一節に次の御言葉があります。
「求めなさい。そうすれば、与えられる。探しなさい。そうすれば、見つかる。門をたたきなさい。そうすれば、開かれる」(マタイによる福音書7章7節)。
シンプルな言葉で構成される「山上の説教」は、どれも心にスッと入ってきます。しかし、この御言葉を実際の経験に当てはめると、どうでしょうか。人によっては、「なんだか腑に落ちない!」と思われるかもしれません。つまり、こういうことです。
求めているのに、与えられない。
探しているのに、見つからない。
叩いているのに、開かれない。
もし本当にそうなら、キリストが語られたことは所詮、絵に描いた餅にすぎない、ということになってしまいます。
天の国の秘密?
実は、この御言葉とほぼ同じ言葉が、ルカによる福音書11章に登場します。しかしこちらは「山上の説教」の後、あらためて弟子たちに語られたもので、後半の一部も異なります。
では、なぜキリストは、一部異なる御言葉を弟子たちに語られたのでしょうか。その理由は、「あなたがたには天の国の秘密を悟ることが許されている」(マタイによる福音書13章11節)とあるように、弟子たちには一歩踏み込んで語る必要があったからです。天国の秘密ですから……ここを読むと「山上の説教」の御言葉が腑に落ちてくるから不思議です。
では、その異なる部分を比較してみましょう。
群衆に→「まして、あなたがたの天の父は、求める者に良い物をくださるにちがいない」(マタイによる福音書7章11節)。
弟子に→「まして天の父は求める者に聖霊を与えてくださる」(ルカによる福音書11章13節)。
キリストはルカによる福音書11章で、「祈り方を教えてください」という弟子の求めへの回答として、真に祈り求めるべき究極の“良い物”とは何かを教え、さらに“祈りの真髄”をも教えられたのです。
良い物とは?
キリストは弟子たちに、“良い物”とは聖霊、すなわち御霊なる“神ご自身”であることを明らかにされました。エレン・ホワイトの次のコメントは、その理由を理解する助けとなります。
「わたしたちがいつどんな時でもお願いできる(祈れる─著者による付加)というのは、わたしたちが大きな必要に迫られていて、神と神の贖いの力がなければどうにもならない状態に陥っているからである。『捜せ』。神の祝福だけでなく、神ご自身を求めなさい」(『祝福の山』より)。
私たちの地球は、天地創造の直後に罪が入り込んで以来、死のパンデミックという“どうにもならない”異常事態の中にあります。今までどれだけの人々が、永遠の死へと追いやられたことでしょう。
しかし、そのパンデミックの真の恐ろしさは、そこに“悪意”があるということです。ゆえに、その手口は卑劣を極め、人々を無自覚のまま、次々に滅びへと導いているのです。
「身を慎んで目を覚ましていなさい。あなたがたの敵である悪魔が、ほえたける獅子のように、だれかを食い尽くそうと探し回っています」(ペトロの手紙一・5章8節)。
二千年前、父なる神はこの恐ろしい敵に対し、まずキリストを送り、次に御霊をも送ってくださいました。この出来事は、この世界に蔓延した罪にいよいよ終止符を打つ時が来たことを意味します。しかし、その分、敵は死に物狂いで抵抗しているということです。
コロナ禍にある今、立ち止まって、その現実に目を向けよと言われているような気がします。改めて、私たちは今、何を求めるべきなのでしょうか。
祈りの真髄とは?
人は“困った時の神頼み”で、御利益のありそうなものにすぐ手を合わせます。しかし現実を知っている私たちは、それと同じレベルに留まっていてはなりません。
もし、求めているのに与えられない、探しているのに見つからない、叩いているのに開かれないと感じているなら、次の3つの御言葉に照らしながら、自分が今まで何を求め、誰を探し、どこを訪ねてきたかを確認してみましょう。誌面の都合上、御言葉の一部しか載せられませんでした。ぜひ、実際に聖書を開いて確認してください。
①求めても与えられないとき(ヤコブの手紙4章2、3節)
「得られないのは……間違った動機で願い求めるからです」
②探しても見つからないとき(ヨハネによる福音書5章39、40節)
「聖書はわたしについて証しをするものだ。それなのに……わたしのところへ来ようとしない」
③叩いているのに開かれないとき(ヨハネによる福音書16章23、24節)
「今までは、あなたがたはわたしの名によっては何も願わなかった」
スッキリと目が覚めたでしょうか。キリストが弟子たちに教えられた祈りの真髄をひとことで言えば、“誰を訪ねるか”というものでした。つまり門を叩く(祈る)とは、私たちの必要に本当に応えることのできる方の家の前まで行って、“イエス・キリスト”という表札が掛けられているのを確認し、確信をもって叩く、ということです。
エレン・ホワイトが、「『捜せ』。神の祝福だけでなく、神ご自身を求めなさい」と言われたのは、そういうことです。
的外れな祈りをしている場合ではありません。キリストのもとへ行き、キリストの名を呼んで求めましょう。そうすれば、与えられます。

柴田寛/しばたひろし
千葉県袖ヶ浦市出身。1971年、文書伝道者の家庭に生まれ、今月で50歳になる。説教は苦手だが、聖書研究をしているときに幸せを感じる。2019年から、福岡教会、芦屋教会、春日原集会所、小倉集会所を担当。妻、娘2人、息子1人の5人家族。
アドベンチスト・ライフ2021年5月号