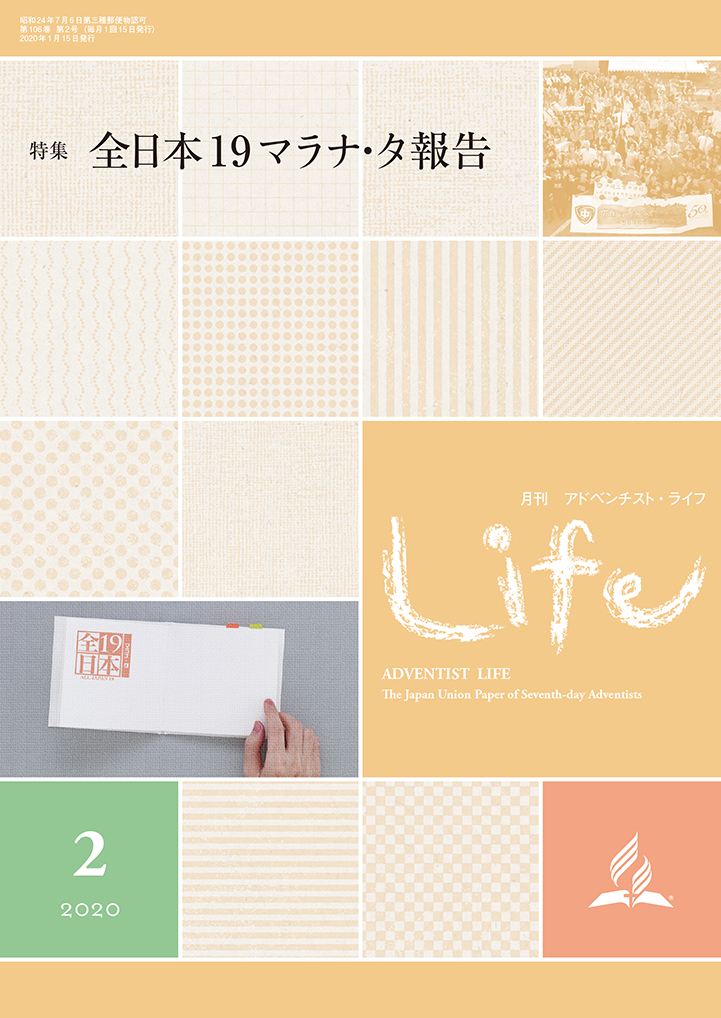「このように、わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており、このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています。そればかりでなく、苦難をも誇りとします。わたしたちは知っているのです、苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを。希望はわたしたちを欺くことがありません。わたしたちに与えられた聖霊によって、神の愛がわたしたちの心に注がれているからです」
(©︎日本聖書協会 ローマの信徒への手紙5章1~5節)
ヘブライ人の中のヘブライ人
パウロは、「わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており」と言っています。これは、非常に美しい聖句だと思います。このような言葉を発することのできる人は幸いです。
しかし、かつてのパウロはそうではありませんでした。パウロは自らの出自について、「生まれて八日目に割礼を受け、イスラエルの民に属し、ベニヤミン族の出身で、ヘブライ人の中のヘブライ人」(フィリピの信徒への手紙3章5節)と言っています。さらに「律法に関してはファリサイ派の一員、熱心さの点では教会の迫害者、律法の義については非のうちどころのない者でした」と律法の命じることを完璧に実行できると信じ、自分の義を自分で達成することができるとうぬぼれていました。
このように生きていた頃の彼は、自分以外の考え方や生き方をする人たちを認めることができませんでした。彼の心の中には、そういった許しがたい人々を非難したり、攻撃したりする言葉が心の中で渦巻いていました。ですから、かつての彼は幸せであったはずがありません。
義とされるのは行いではない
回心前のパウロは、「人を愛するためには当時の慣習を破ることもあえてした」というキリストの生き方や、キリストに従う人々の生き方を許すことができませんでした。それは、「神聖な律法に対する冒瀆である」と考えて厳しく批判をし、キリストに従う人々に対しては厳格な処罰が必要である主張し、彼らを処罰するためにダマスコへ向かいました。
しかし、その途中で「サウロ、なぜ、わたしを迫害するのか」というキリストの声を聴き、パウロは打ちのめされました。地べたに倒れて、目が見えなくなり、何も食べられない状態に陥りました。今までの生き方はまるで違っていたということを知らされて、深刻な反省を迫られたのではないかと想像します。この辛い経験を通して初めて、「人が義とされるのは行いなのではない」という真理にパウロは目覚めたのでした。ですからパウロは、「わたしたちは信仰によって義とされたのだから、わたしたちの主イエス・キリストによって神との間に平和を得ており」と告白しているのです。
この言葉の中には、言葉としてはっきりと出てくるわけではないのですが、パウロ自身の罪の悔い改めが出てきているように思えます。パウロは、「私は今まで間違った生き方をしていた。しかし、信仰によって義とされることによって、神との間に初めて平和を得ている」と言外に告白しているのではないかと思います。パウロはすべてから解放されて、彼は謙虚になったのです。
神に頼るしかない
私たちが謙虚になってキリストを見上げ、自らの罪を認める。そして、その罪を告白して心から赦しを請う。その時に初めて神との間に平和が戻ってきます。パウロは実際にそのような経験をしたことでしょう。ですから、彼はこう言うのです。「このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りにしています」(©︎日本聖書協会 ローマの信徒への手紙5章2節)。
さらにパウロは、「そればかりではなく、苦難をも誇りとします」と言っています。ここで言われている「苦難」という言葉は、「圧迫」とも訳されている言葉です。コリントの信徒への手紙二に出てくる、「兄弟たち、アジア州でわたしたちが被った苦難について、ぜひ知っていてほしい。わたしたちは耐えられないほどひどく圧迫されて、生きる望みさえ失ってしまいました」(1章8節)という「圧迫」です。耐えられないほどひどく圧迫される、つまり彼を迫害する人や、彼に悪口を言ったりする人がいる。その中でどんなに彼が苦しんだことか、時々生きる望みさえ失ってしまったと彼は言うのです。そして、パウロはこのような状況について、「死の宣告を受けたと同じようであった」(1章9節参照)と言っています。
そのような苦難の中で、自分を頼りとすることなく、死者を復活させてくださる神を頼りにするようになったのです。それは、パウロがダマスコへの途上で経験したあの深い悔い改めの経験を通して、「もう神に頼るしかない」ということを見いだしたのです。苦難を誇りにするという言葉の意味はそこにありますし、なぜ苦難を誇りにすることができたのかという理由はまさにここにあったのでしょう。ですからパウロは言うのです。「わたしたちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生むということを」
このことを知り、そこに導かれるときに、私たちはどんなことがあっても、主が私たちをまた迎えに来るその日まで、この地上での生活を全うすることができるのでしょう。
終わりの時代を生きている私たちは、今、苦難を誇りとすることができるよう備えなくてはいけません。キリストが私たちのために十字架にかかり、私たちのすべての罪を洗い流すために死なれました。キリストにすべてを委ねるとき、私たちは苦難を誇りとすることができます。キリストの十字架を心の中心に掲げ、来るべきキリストの再臨の日に備えたいと思います。
「キリストは信仰によってご自分を受け入れる者のうちにお住みになる。試みが魂に訪れようとも、主の臨在は私たちと共にある。主の臨在のしるしであった燃える柴は燃え尽きなかった。火は枝の繊維を焼き尽くすことはなかった。キリストに信頼を寄せる弱々しい人間も同じである。誘惑の火が燃え、迫害と試練が来ようとも、燃え尽きるのは不純物だけである。浄化されることによって、金はいっそう明るく輝く」(Signs of the Times Mar. 5 1896)。

藤田佳大/ふじたよしひろ
三育学院カレッジ神学科卒業、アドベンチスト国際神学院修士課程修了。高知、土佐山田、徳島の各教会を歴任。
2019年4月より三育袖ヶ浦教会牧師。
三育学院カレッジ神学科歴史神学非常勤講師。
アドベンチスト・ライフ2020年3月号